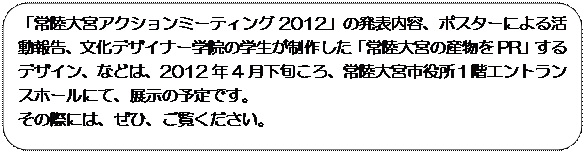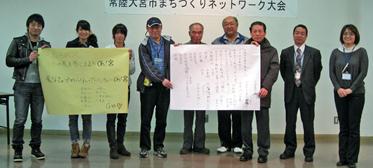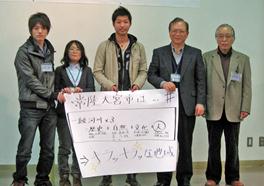日時:2012年3月3日(土) 13:00〜
会場:おおみやコミュニティセンター
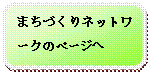 13:00〜14:50 常陸大宮アクションミーティング2012
13:00〜14:50 常陸大宮アクションミーティング2012
15:00〜17:40 第3回 常陸大宮市まちづくりネットワーク大会
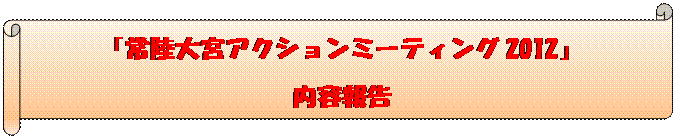
|
今年度も、常陸大宮市をフィールドに研究を行った茨城大学学生による研究発表会「常陸大宮アクションミーティング2012」が、2012年3月3日(土)、おおみやコミュニティセンターで、開催されました。当日は、多数の市民の方たち、三次真一郎市長に参加いただきました。 アクションミーティングの特徴は、卒業研究として常陸大宮市をフィールドとした4年生による発表だけでなく、学部の1年生から大学院生まで幅広い学年の、また、地域研究から文学研究まで多様な分野を専門とする学生による発表が行われることです。つまり、それだけ多様な観点からの研究発表が行われます。今年度のアクションミーティングでも非常に多彩な発表が行われましたので、以下、紹介していきます。 発表題目:常陸大宮の新たな創作料理ができました!!! −1枚の畑と水戸市自由広場を結んだ広域ネットワーク− 発表者:津田彩織(茨城大学人文学部社会科学科4年)(卒業研究) 概要:常陸大宮市をフィールドした卒業研究の発表でした。2010年11月6日に水戸市の自由広場にて「アルベトレッペ食堂」という食のイベントが開催され、そのうち3つのブースで、常陸大宮市で生産された食材を使用した創作料理が出品されました。津田さんは、その料理を創作した様々な人々のネットワークがどのように構築されていったのかを詳細に分析しました。その結果、常陸大宮市と地域連携協定を結ぶ茨城大学人文学部の学生や教員が、生産物を提供した市内の様々な生産者と、料理を調理した水戸の大成女子高校、そしてイベントで出品する際のデザインを行った文化デザイナー学院の学生たちを結びつけたことで、料理が創作されたことを明らかにしました。また、市内の生産者の方々の多大なサポートは、長期間かけて少しずつ深化してきた市内での様々な活動に基づいた市民と茨城大学との良好な関係によるものであることも指摘されました。さらに、多くの自治体で公的な空間の利用方法が模索される中で、多様な人が気軽に集える広場としての利用は、人と人との関係の希薄化が進む現代社会には必要なのではないかと提言されました。津田さん自身、3年生から常陸大宮市の学生活動に参加してきたということもあり、重厚な内容の発表でした。 発表題目:やるしかないっしょ!つながるっしょ!ひたちOh☆宮 −交流活動に取り組む市民グループと学生の協働についての分析− 発表者:POS(茨城大学人文学部社会科学科小原ゼミ3年) 概要:POSとは、「Project of Shiota」を意味するそうです。その名の通り、塩田地区にて都市農村交流事業のサポートをしながら、休耕地を利用して農業を行い、地区の方々と交流することで、地区をより元気にしようと取り組んでいる、3年生を中心とした学生グループです。塩田地区のほかに、盛金地区や岩崎地区にて交流に取り組む市民グループについても取り上げ、それぞれの市民グループの活動の特徴と問題点が指摘されました。 非常に元気な学生グループによる、刺激的な内容の発表でしたが、学生たちの常陸大宮市への愛着がひしひしと伝わってくる内容でした。 アクションミーティングに参加された市民の方々からの反響は大きく、今後の展開が楽しみな発表でした。 発表題目:地域活性化の活動を発信しよう、知ってもらおう!! 発表者:小林美咲姫(茨城大学大学院人文科学研究科1年) 立花将太(茨城大学人文学部社会科学科4年) 概要:人文科学を専攻する大学院生である小林さんと社会科学専攻する4年生の立花君という異色のタッグによる発表でした。専攻も学年も異なるお二人は、常陸大宮市での学生活動への参加をきっかけに共同研究を行ったそうです。上級学年による研究ということで、落ち着いた、しかし内容の濃い発表でした。具体的には、いかに学生と市民による地域活性化の活動を持続可能なものにするかというテーマでの研究でした。その結果、学生と市民との関係は強いものとなりつつあり、活動内容も量も質も充実したものになっているが、その活動を外に発信していくことが必要であることが指摘されました。外に発信していくのは、もちろんより多くの人たちに常陸大宮市での活動を知ってもらい関心をもってもらうことで新たな可能性が生まれるからですが、それと同時に重要なのが、学生時代に常陸大宮市での活動に取り組み、常陸大宮市の魅力や活動の意義を知っている茨城大学を卒業していったOBやOGに発信していくことで、4年間という短い期間だけでなくその後も関心を持ち続けてもらうことで持続性が高まるからだと指摘されました。気付きそうで、なかなか気付くことのできない点が指摘され、学生と市民の活動がより発展する可能性が提示されました。
|
|
|
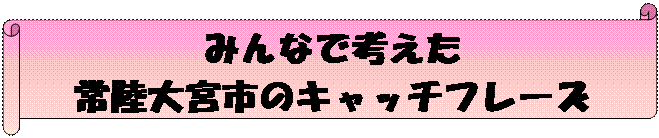
|
「第3回 常陸大宮市まちづくりネットワーク大会」では、登録団体の中から、2つの団体に、最近開設されたカフェのお話をしていただきました。オープンまでの経緯、今後の展望などをお聞きし、会場から出された質問に答える形で意見交換を行いました。 「学校カフェまんまの紹介」盛金WAC協議会(川野辺耕機さん) 「コミュニティカフェから街づくりへ〜地域住民と作る地域活性化プラン〜」 フロイデDAN(寺門貴さん)(コミュニティカフェ バンホフ) 後半は、参加者約90名が8つのチームに分かれ、「常陸大宮市のキャッチフレーズを作ろう!」をテーマにワークショップを行いました。常陸大宮市の魅力、自慢、素敵なところをたくさん挙げながら意見交換をし、以下のようなキャッチフレーズができあがりました。 市民の方たち、茨城大学の学生、市の職員など、経験や年齢もさまざまなメンバーによるチームでの話し合いはとても楽しく、活発な意見交換ができました。 各チーム自信満々のキャッチフレーズです。現在の常陸大宮市の魅力を再発見し、確認しただけでなく、将来・未来に向けて、どのようなまちであってほしいか、どのようなまちを目指していくか、ということが参加者の心に、明確になったと思います。 会の終了後、みなさん、すばらしい笑顔で、再会の約束をしていました。 <キャッチフレーズ> ●まずは来てみてDEEPな魅力!! 常陸大宮 ●宝探しができる郷(まち) ●見つけよう 育てよう 広げよう 常陸大宮市 ●常陸大宮市は キラッキラッな土地 ●都会では味わえない懐かしの原風景へタイムスリップ常陸大宮 ●むすびの里山 ひたちOh!宮 ●来たらがっぺ 四季の実(みのり)を感じるまちOh!宮 来なきゃ分からないアドベンチャーOh!宮 ●やさしいまち、常陸大宮
|
|
お問い合わせは、 常陸大宮市 市民部市民協働課 TEL 0295−52−1111(代) このページに関するお問い合わせは、 茨城大学人文学部 西野研究室 Lastupdated 20110506 (C)常陸大宮市まちづくりネットワーク事務局 All Rights Reserved. |